研究成果詳細
新方式の3次元電極でバイオ燃料電池の性能を劇的に向上
要約
本学資源化学研究所の山口猛央教授らのグループは,血中にも存在する糖であるグルコースを燃料に使う「バイオ燃料電池」の出力電流を従来の6倍に増やすことに成功した.この成果については2009年3月開催の化学工学会と電気化学会で発表した.研究の内容,背景,意義,今後の展開等
本学資源化学研究所の山口猛央教授らのグループは,血中にも存在する糖であるグルコースを燃料に使う「バイオ燃料電池」の出力電流を従来の6倍に増やすことに成功した.この成果については2009年3月開催の化学工学会と電気化学会で発表した.
生体内での解糖系と同じ反応を発電に利用
バイオ燃料電池は,ヒトの体内でグルコースを二酸化炭素にまで分解する解糖系と同じ反応過程の一部を発電に利用する(図1).工学的には,糖を酸化する酵素(グルコースオキシダーゼ)を電極につけた血糖値センサーと基本的には同じであるが,大量の電気に変換するという目的が異なる.メタノールを使うDMFCとは違い,燃料から最終生成物までに発生する物質が体内で代謝される物質と同じであり安全性が高い.また酵素の大量生産は容易であり,将来的には人体に安全・安心な燃料電池としての応用が検討されている.
しかしこれまでのバイオ燃料電池は,出力電流が数μA/cm2程度しか取れないという欠点があった.携帯向けに研究が進むDMFCなどの出力(1~数A/cm2)には及ばない.バイオ燃料電池では,酵素だけではなく,グルコースと酵素が反応する活性中心から効率よく電子を集めるために,ビニルフェロセニンなどの分子(メディエータと呼ぶ)を介在させる.このメディエータの電子伝導度が低い(カーボンの1万分の1)ために電流が増やせなかった.
効率よく電子を収集する3次元構造電極を作成
解決策には,メディエータとして電子伝導速度の大きなオスミウム錯体を使う方法もあるが,オスミウムは白金同様に貴金属であるうえに,その錯体は人体に有毒であり,反応過程で(体内にも存在する)無毒な物質しか生成しないというバイオ燃料電池のよさを損なう.また,性能の限界も見えてきていた.そこで山口教授らは電極の構造を変えて,メディエータから電極(カーボン)までの距離をできるだけ短縮することを考えた.一方,現在使っている酵素は,カーボンの疎水性表面に直接載せると変性・失活する.そしてグルコースと酵素を効率よく接触させるには,平面上に酵素を配置するよりも立体的に配置したほうがよい.
そこで山口教授らは,カーボン基板上にまず30nmのカーボン小球を載せ,その表面に親水性のあるアクリルアミドの枝を共重合(グラフト共重合)によって生やし,その枝にメディエータと酵素を付着させるという3次元構造の電極を考案した(図2).事前のシミュレーションでは,DMFCなみの数100mA/cm2の出力が可能という予測が出たという.
ところが最初に試作した電極の単位面積あたり出力は,2mA/cm2にとどまった.原因としては酵素の付着数が少なかったか,ほとんどが失活していると考えられた.「透過型電子顕微鏡(TEM)による観測で酵素の付着数が十分なことを確認できたので,酵素が失活しているのではないかと推測した.電極に付着させたままで酵素の活性を調べることはできないが,別の検証実験によって,カーボン表面(疎水性の部分)に酵素が付着すると変性・失活することを確かめた」という.こうした検証を踏まえ,新たにカーボン表面の親水性基を増やす処理を加えたところ,出力電流を12mA/cm2に引き上げることができた.
DFMCなみの出力も手が届く範囲に
今後さらに出力を増やす工夫としては,表面の親水性をさらに高めたり,酵素同士を架橋したりする方法が考えられる.山口教授は「酵素同士を架橋しても活性が失われないことは既に確かめた.酵素の環境を良くすることで全体の8割から9割が活性を維持できるようにすれば,直接メタノール燃料電池(DMFC)に迫る数100mA/cm2の出力が可能になる」という.
山口教授は「バイオ燃料電池の実用化にはあと3つくらい山を越さなければならない」という.最大の課題は寿命である.酵素センサーの場合はだいたい数年で寿命が来るが,バイオ燃料電池の寿命はさらに短く,数カ月程度だからだ.メタノールを持ち込めない医療現場での利用が考えられる.将来の夢として酵素を補充したり電極構造を更新したりする仕組みが整えば,生体ロボットのエネルギー発生装置として使うことも考えられる」と語っている.
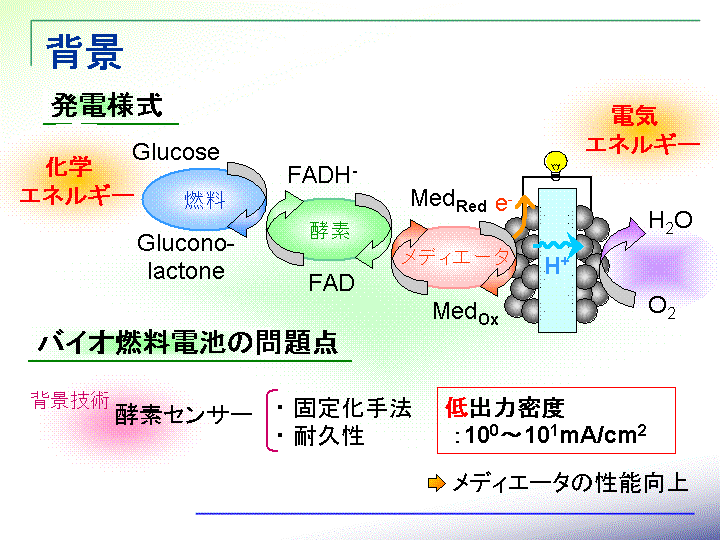 | 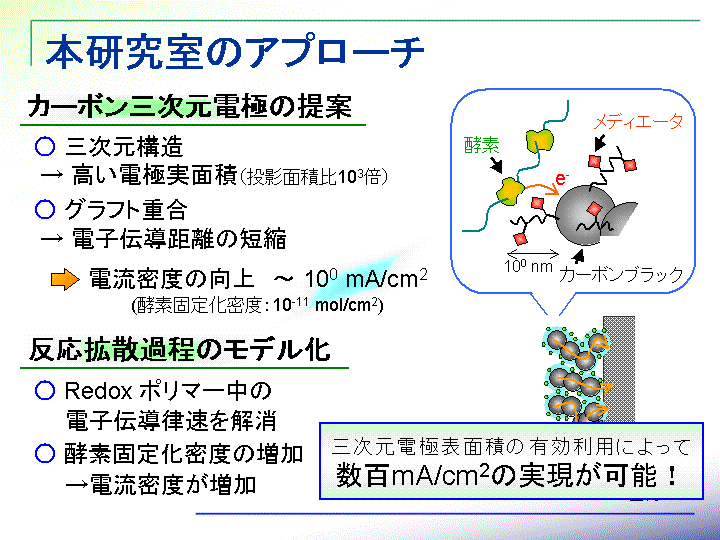 |
| 図1 バイオ燃料電池の発電様式と課題 | 図2 開発した3次元構造電極の模式図 |
| 本件に関するお問い合せ先 |
|
|---|---|
| TEL | |
| FAX | |
| URL |
*6年以上前の研究成果は検索してください
