研究成果詳細
安全性と低コスト両立した次世代高速増殖炉用発電技術にめど
要約
東京工業大学原子炉工学研究所の有冨正憲所長らの研究グループは、ナトリウム冷却高速増殖炉(FBR、用語2)からの熱を超臨界状態の二酸化炭素(用語1)に伝え、高効率で発電する超臨界二酸化炭素ガスタービン発電の実現にめどをつけた。同発電システムの基幹技術であるターボ圧縮機の二酸化炭素臨界点近傍における安定運転と運転性能の確認に成功したもの。FBRの次期実証炉では蒸気タービンによる発電が想定されているが、ナトリウム・水反応(用語3)の危険性を回避する対策が必要なため、経済性を飛躍的に向上させるのは難しい。そこでナトリウム・水反応のような激しい反応を生じず、かつ高い発電効率を達成できる超臨界二酸化炭素ガスタービン発電が安全性・経済性を両立するFBRとして世界的に注目されている。
研究の内容,背景,意義,今後の展開等
東京工業大学原子炉工学研究所の有冨正憲所長らの研究グループは、ナトリウム冷却高速増殖炉(FBR、用語2)からの熱を超臨界状態の二酸化炭素(用語 1)に伝え、高効率で発電する超臨界二酸化炭素ガスタービン発電の実現にめどをつけた。同発電システムの基幹技術であるターボ圧縮機の二酸化炭素臨界点近 傍における安定運転と運転性能の確認に成功したもの。
FBRの次期実証炉では蒸気タービンによる発電が想定されているが、ナトリウム・水反応(用語3)の危険性を回避する対策が必要なため、経済性を飛躍的 に向上させるのは難しい。そこでナトリウム・水反応のような激しい反応を生じず、かつ高い発電効率を達成できる超臨界二酸化炭素ガスタービン発電が安全 性・経済性を両立するFBRとして世界的に注目されている。
今回、実用化に向けて残された最後の課題である二酸化炭素の物性値が急激に変化する超臨界点近傍での圧縮機の運転安定性と運転性能の確認を行うため、小 型遠心圧縮機モデル試験を文部科学省の「原子力システム研究開発事業」の受託事業として実施している。その結果、圧縮機は安定に運転できること、臨界点近 傍では他領域に比べて著しく小さな動力で圧縮できることを確認した。これにより、実用化に向けた課題がすべて解決、今後、実用化に向けて世界初となる超臨 界炭酸ガスタービンシステムの運転制御技術の確立を目指した発電原理実証試験を行っていく。
●本研究で得られた結果・知見
◇超臨界点近傍で作動する圧縮機の性能及び健全性
実用化上大きな問題とされた臨界点近傍での圧縮機運転性能の不安定性について、超臨界二酸化炭素圧縮機小型モデルを試作し、運転試験を行うことによりその安定性に関する検証試験を実施した。
図9に圧縮機により圧力を超臨界点圧力(7.2MPa)近傍で一定に保ったまま圧縮比を徐々に増加させた場合のエンタルピー変化を示す。これによると、臨 界点圧力以下(3.5~6.5MPa)に比べて臨界点圧力以上(8MPa)の場合、同じ圧縮比を達成する際に必要とされる仕事量が大幅に低減される(エン タルピー増加量が小さい)ことが確認された。
図10に圧縮機により超臨界点圧力(7.2MPa)以下の二酸化炭素を連続的に昇圧し、臨界点圧力を越えて臨界点圧力に至った際の圧縮機入口・出口圧力変 化を示す。これによると、圧縮機入口において臨界点圧力以下の二酸化炭素が圧縮機により昇圧され、出口圧力において臨界点圧力を越えてからも一定圧力を維 持しており、圧縮機出口圧力に特段の不安定性も認められない。このことから、超臨界点圧力近傍の不安点領域において圧縮機運転性能の安定性を損なう事象が 発生せず、圧縮機を安定に運転制御できることが明らかとなった。
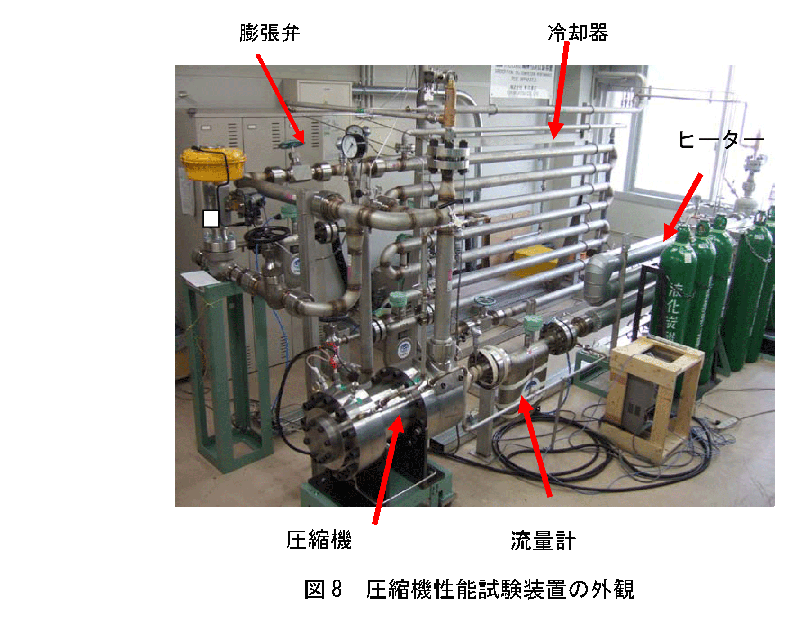 | 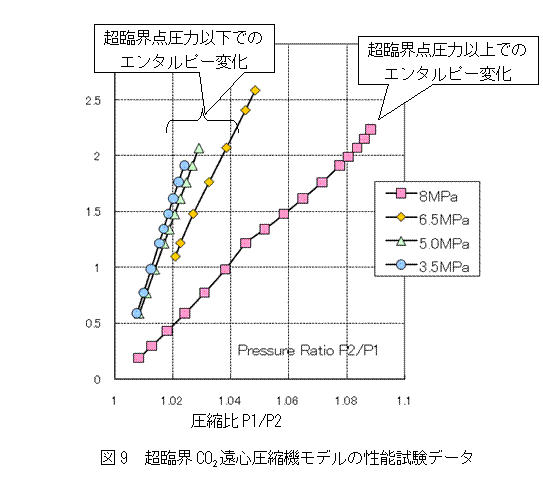 | 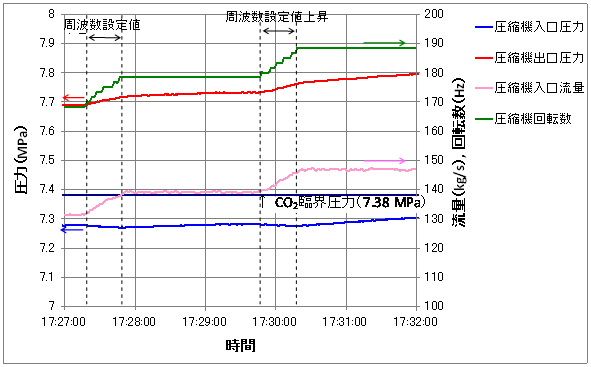 |
| 図8 圧縮機性能試験装置の外観 | 図9 超臨界CO2遠心圧縮機モデルの性能試験データ | 図10 超臨界点上下近傍での圧縮機の連続運転データ |
◇超臨界点近傍で作動する圧縮機の性能及び健全性
超臨界においては、通常の温度、圧力とはガスの化学的活性が異なってくることから、超臨界二酸化炭素雰囲気中で金属材料が想定する寿命期間中、健全性を保 てるかどうかを試験により確認しておくことが重要であり、図11に示す装置を用いて、12Cr鋼と316FR鋼の2種類の高速炉の候補構造材料で最大圧力 20MPa、最高温度600℃の耐食性試験を実施中である。これまでの試験結果では、316FR鋼については部分的に酸化が観察される程度であり、良好な 耐食性を示すことが確認されている。また、12Cr鋼については、CO2による酸化が進行しやすいものの、その挙動は長時間にわたって安定に推移する傾向にあることが確認されている。
 |  |
図11 超臨界CO2中材料腐 食試験装置構成概略図 | 図12 材料試験片の腐食量 (重量変化)測定結果 |
【用語解説】
1. 超臨界二酸化炭素
温度と圧力の関係において気体と固体との三重点以上(温度31℃、圧力7.38MPa)の状態で、気体の拡散性と液体の特性を併せ持つ高密度物質である。超臨界二酸化炭素は様々な物質をよく溶解することからコーヒーの脱カフェインなどに使用される。
2. ナトリウム冷却高速増殖炉(FBR)
溶融ナトリウムで原子炉を冷却する方式の高速増殖炉であり、原子炉で燃えてなくなるウラン235燃料よりも、より多くの量の新しいプルトニウム燃料をウラン238から原子炉を運転しながら作りだす、いわゆる増殖が可能な原子炉である。
3. ナトリウム-水反応
ナトリウムは98℃で溶融し、非常に反応性の高い金属で、酸、塩基、水と激しく反応する。水と反応して水素を発生しながら水酸化ナトリウムになる。一方で、熱伝導率が高く、高温でも液体で存在するため高速増殖炉の冷却材として用いられている。
| 本件に関するお問い合せ先 |
|
|---|---|
| TEL | |
| FAX | |
| URL |
*6年以上前の研究成果は検索してください
